
日本の出版文化を東京・神保町から世界に向けて発信していくことを目的に結成された神保町文化発信会議は1月22日、第2回神保町シンポジウム「出版文化の神保町 世界に飛翔するために」を東京・千代田区の出版クラブビルで開催した。
今後の課題や展望を語り合うパネルディスカッションも行われ、鹿島茂氏(作家、フランス文学者)、林真理子氏(作家、日本大学理事長、日本文芸家協会理事長)、切通理作氏(ネオ書房店主、評論家)、柴野京子氏(上智大学教授)の4人がパネリストで登壇。吉見俊哉氏(東京文化資源会議会長、国学院大学教授)が司会を務めた。
鹿島氏は、自身が総合プロデュースしている神保町のシェア型書店「PASSAGE(パサージュ)」を紹介。「2022年3月に1号店をオープン。現在、4号店まで増えており、棚数も合計で1000を超えている」とPRした。
林氏は「私の母は小さな本屋を営んでいた。私も本を仕入れる父に連れられて、よく神保町に来ていた。そして、日本大学の理事長となってからは、学生と本を結びつけたいと思い、さまざまな取り組みもしている。日大も一緒に神保町を盛り上げていきたい」と表明。また、街の本屋さんが無くなっていることについて、「街の品格は本屋があることだと思っている」と訴えた。
評論家の切通氏は、阿佐ヶ谷ネオ書房、神保町ブックカフェ二十世紀で古書販売、展示、イベント企画などを運営している。「古本はそこそこ売れるが、新刊を置いても全然売れない。ただ、出版イベントを催し、著者がサインしたりすれば売れる。イベントなどさまざまな企画を連動させて、売れる角度をつけることが大事」と話した。
柴野氏は「書店数が減っている一方で、インディーズ系の本屋は増えている」とした上で、「ネット書店ができて、読者は本の在庫に直接アクセスできるようになり、本を探す主体が読者に移ってきた。ネット上には全ての本の情報が開示されていて、平均的で部分的な品ぞろえをする既存書店が難しくなってきている。一方、それとは正反対のセレクト的な書店が価値を持つようになってきている。これも読者側の変化があるし、小さい規模での仕入などができるようになったことも大きい」と分析した。
「もの」としての本は生き残る
それを受けて、鹿島氏は「私も今後の未来像を考えてみた。これからは文庫や新書といった価格が安い本は、どんどん淘汰されていくだろう。私もずいぶん出しているが、文庫を絶版にする出版社が増えてきている。本は全て単行本で高価なものという時代が来る。そうなると、全てを網羅した大書店か、何かに特化した超専門店しか生き残れないだろう」と予想。
そして、「最終的に、『もの』としての本は生き残ると考えている。私もフランスの古い本を集めているが、それらはフランスの国会図書館でもオンラインで無料公開している。誰でも見られるのに、実際の本の値段は上がっている。『もの』として持つことと、『情報』として持つことは完全に分化されている」と指摘した。
林氏も「良いか悪いかは分からないが、今は本が高尚な趣味として扱われている。例えば、本が好きと言って知的さをアピールする芸能人もいる。本来、本は娯楽のひとつだったはず。神保町という知的な空間で特別な一冊を買うのもいいが、かつて実家の本屋で誰もが娯楽として本を手に取っていたのを思い出すと、複雑な気持ちになる」と話した。
神保町の街について話がおよぶと、鹿島氏は「神保町はサブカルの価値を再発見できるシステムができあがっている。それを絶やさないために何ができるかを考えている」と、林氏は「10年に閉館した日大カザルスホール(東京・お茶の水)も復活させたいと思っている。設計はしてあるので、一日も早く(神保町の)お役に立てるホールにしたい」と語った。
柴野氏も「林さんが古本屋は入るのに勇気がいると心理的なバリアの話もしていたが、物理的なバリアフリーも必要だ。地下鉄のエレベーターも少ないし、狭い古書店も多い」と課題を示した。


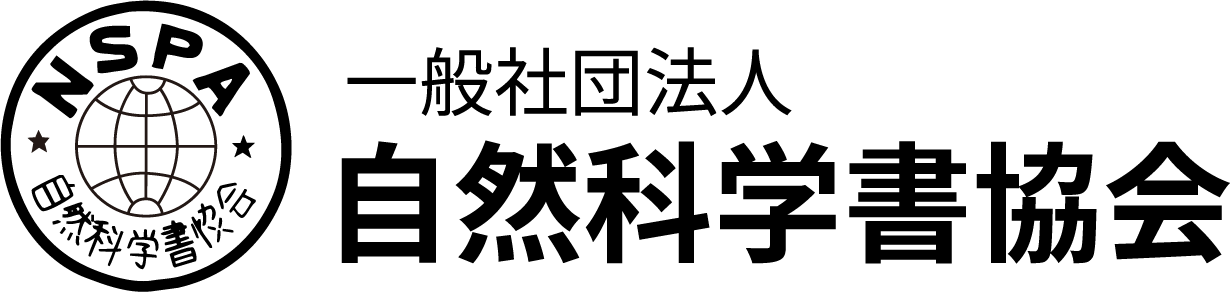
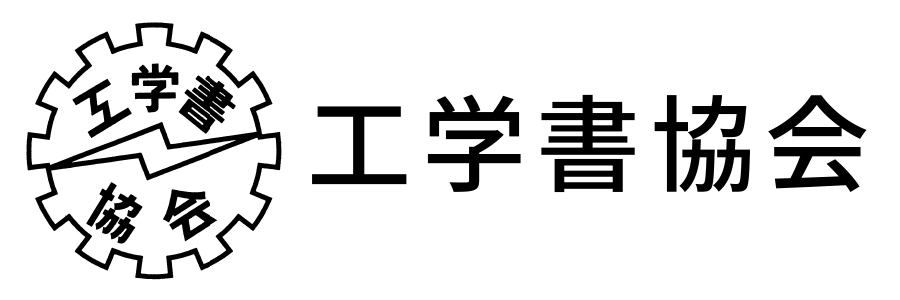
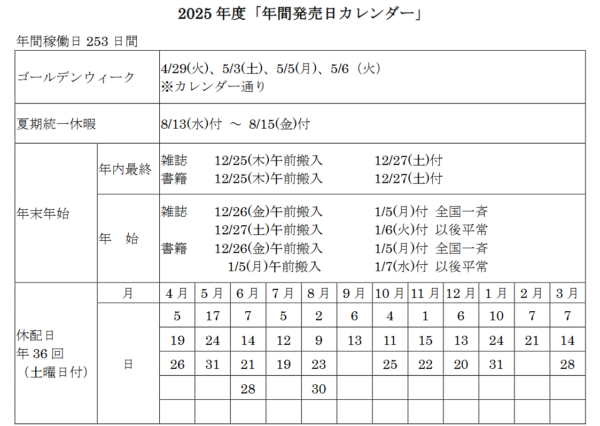
コメント