「小泉今日子」親衛隊の少年たち
80年代の熱狂と青春の儚さを描く

中央公論新社が9月上旬に刊行した『オートリバース』は、1980年代、アイドルを独特なスタイルで応援する「親衛隊」をテーマにした青春小説。当時の親衛隊は、学校や家に居場所が見つけられない少年たちの救いの場だった。本書は、新人アイドル「小泉今日子」が親衛隊とともにデビューからトップアイドルへと駆け上がるまでのひとつの時代を描いた作品だ。小泉今日子さん自身から当時の親衛隊の話を聞き、ペンをとったという高崎さん。なぜ広告クリエーターが小説を書こうと思ったのか。またタイトル『オートリバース』に込められた思いとは。
電通で話題のキャンペーンを数々手がける高崎さん。JR東日本の「行くぜ、東北」も彼の仕事だ。小泉今日子さんと仕事をする機会があり、彼女から聞いた親衛隊の少年たちの話が本書執筆のきっかけだという。昔から小泉さんのファンだった高崎さん。今でも彼女は特別な存在だという。
企業の「ラブレターの代筆」とよく言われますが、クライアントが多くの人に、何を言いたくて、どう伝えたいのか、それをデザインするのが主な仕事です。
小泉さんともいろいろとお仕事させてもらう中で、彼女がアイドルとして活躍していた当時の親衛隊の話を聞いたんです。親衛隊は不良の集まりではあったけど、とても純粋でいい話もたくさんあるのに、それがどこにも残っていないと仰っていて、それなら僕が書きたいと言ったのがきっかけですね。
僕にとってキョンキョン(小泉今日子さんの愛称)は、女神なんで。何度も仕事もして、お会いもしてるんですが、最初の方はもう目の前にキョンキョンがいるというだけで、「あわわわわ…」ってなってしまって、何も話せず、帰ってくるみたいなことがよくありました(笑)。
・小説は「純度」を保つ表現
広告業界のみならず、これまで映画の脚本・プロデュースを手掛けたキャリアも持つ。CM制作と小説表現との違いとは。またなぜ今回、小説という表現を選択したのか。
誰かに何かを伝える手段という意味では、広告も小説も大きな違いはないと思っています。ただこの物語はデリケートかつ純粋なものだと思ったので、その「純度の高さ」をどうしても維持する必要がありました。だから視聴率とか観客動員数とかをあらかじめ想定してつくられるものよりも、自分ひとりで立ち向かえる小説という形を選んだのです。
広告の場合は、ある程度考えるとそれを誰かに話して、客観的な意見をいれて、ブラッシュアップを繰り返します。でも小説は全然違います。過去の記憶など自分のなかにあるものと対峙する時間が異常に長くなる。描きたい物語があるのにそれをなかなか定着させられなくて、ずいぶん気持ち悪くなりました。でも徹底的に自分を追い込むと、ふっと忘れていた過去の記憶に助けられたりするんです。
そのとき自分が何かの媒体になっているという感覚があって、むかし母親に言われた何気ない一言や、今まで全く思い出さなかった小学生のころの教室の一場面を、急に思い出す。実際に作品の中には出てこなくても、不思議なことにそれが筆を猛烈に押し進める原動力になるんです。おそらく「小説を書こう」という回路になったときに、それまで分別していなかった、整理されていなかった記憶なども呼び起こしてくれるのだと思います。
それは極めて個人的な過去の記憶や感情なんですが、不特定多数の「みんな」が思っていそうなことを物語にしていくより、個人的な思いのほうがずっと説得力をもつし、伝わると信じています。
・行間からにじむリアリティ
本書の中には、映像が鮮明に浮かぶシーンが数多く登場する。また登場人物も、嫉妬や見栄、傲慢さなど、リアリティを持つキャラクターが描かれている。
小説を読んでいて楽しい瞬間というのは情景が浮かぶことです。だから今回の本を書くにあたっても、全編そういうわけではないですが、劇性のある場面では、自然と脳内でカメラを回していて、ここはカット割りにした方がいいのか、ロングで長回しにした方がいいのか、ということも意識しましたね。
また多くの人が知っている80年代という時代を舞台にしているので、整合性を取ることには苦労しました。フィクションであっても、実はノンフィクションなのではないか、と読者に思わせることが一番の理想ですから。
だからリアリティのある表現をするために、作中に出てくる渋谷公会堂や早稲田大学などに足を運び、そのスケール感や距離感などを、身体的な感覚に落とし込みました。例えば「坂」の表現一つであっても、それが「緩やか」なのか、「急」なのかで表現は全然違います。だから頭の中のイメージと現場のロケーションの擦り合わせがとても大切です。
小説は情報量が多ければ多いほど、より豊かなものが書けると思っています。それは必ずしも文章には表記されないかもしれませんが、行間からにじみ出るリアリティがあるはずです。
登場人物については、誰を書いていても自分の一部という感覚があります。嫉妬する気持ちや他人に嫌なことを言ってしまう自分など、やはり自分のリアルな感情がヒントになっていて、それは登場人物のキャラクターにも反映していると思います。
自分がこれまで生きてきた上で感じてきた感情や、体験したこと、いろいろな要素を紡ぎ出して、再構築したものがこの作品になっている。それが何より嘘のない書き方だと信じています。
・時代が変わる悲しさと憤り
タイトル『オートリバース』とは、かつて流行したカセットテープの再生機で、A面からB面に自動で切り替わる、当時の最新機能だ。
高崎さんがタイトルにこの最新機能を冠した意図とは。
当時は家庭内暴力や校内暴力が盛んで、大人と子供の関係が捻れていた時代。子供は子供で集まり、組織を作って自立していた。当時のアイドルたちが、そんな子供たちをつなげてくれていたのではないかという気もします。ただしいくら彼らが自立した子供であったとしても、やはり10代です。彼らが力で他人をコントロールし、その力によって自らが滅びていく、その切なさを描きたかったのかもしれません。
タイトル『オートリバース』も、自動的にA面からB面に切り替わるように、青春が終わり、学校を出たら就職するという、時代が勝手に切り変わることのもの悲しさ、憤りを象徴しています。筆が行き詰まったときも、このタイトルが一つの軸として機能し、最終的にはこの『オートリバース』に集約するように意識しながら、物語を書き進めていきました。
好きな書店に書原リバーシティ店をあげた高崎さん。広告は流行を追いかけても周回遅れで、むしろ誰かの強い好奇心が連れてくる。
いい本屋にはその好奇心が溢れているという。
本屋には自分が欲しいもの、求めているもの以外のものが溢れていて、とても豊かで、大切な場所だと思います。例えば女性誌の表紙を見るだけでも、今はこんなブランドやメイクが流行っているんだということがわかり、そうすると世の中がどういう形をしていて、どう動いているのかがわかる。まさに世の中の縮図です。売れていて読みたい本、売れているけど読まない本、売れていなくても読みたい本、いろんな本が溢れている中を歩くことが好きで、常に本屋に行く理由を探しているように思います。
(聞き手 山口高範)

四六判/240ページ
本体1400円
高崎 卓馬(たかさき たくま)
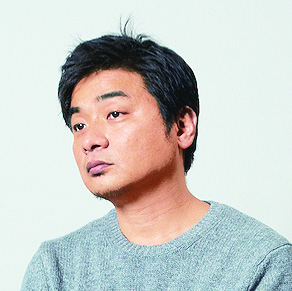
1969年、福岡県生まれ。早稲田大学法学部卒業。クリエーティブ・ディレクター/CMプランナー。JAAAクリエイター・オブ・ザ・イヤーを2度受賞するなど、国内外の受賞多数。最近の仕事に、JR東日本「行くぜ、東北」、サントリーオランジーナ「ムッシュはつらいよ」、三井のリハウスなど。映画『ホノカアボーイ』の脚本・プロデュースやドラマ脚本も手がける。著書に『はるかかけら』『表現の技術』『面白くならない企画はひとつもない 高崎卓馬のクリエイティブ・クリニック』など。

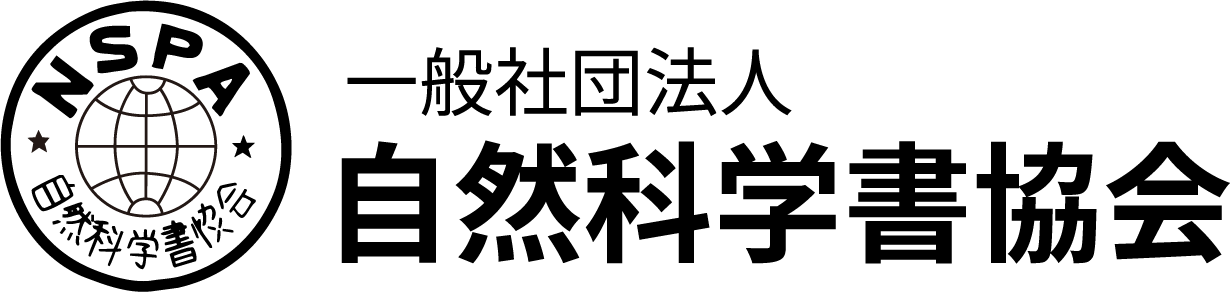


コメント