渋谷テロを題材にした小説が映画化!
エンターテインメントが持つ力とは

人気ドラマ「アンフェア」の原作『推理小説』の著者・秦建日子さんによる、爆破テロの標的となる渋谷を舞台にしたクライムサスペンス『サイレント・トーキョーAndsothisisXmas』。2016年に単行本を刊行、19年に文庫化、そして12月4日には豪華キャストによる映画公開も決まっている。映画監督や脚本家として活躍していながら、「映画制作には口を挟まない」と言う秦さんに、小説と映画化への思い、またエンターテインメントの本質、可能性について話を聞いた。(聞き手山口高範)
クリスマス・イブの夜に爆破テロの標的となる渋谷。秦さんはなぜ、この小説を書こうと思ったのか。
2015∼16年当時、それまで安全だと思い込んでいた世界中の都市や地域でテロ事件が相次ぎました。一方、日本国内に目を向けてみると、なぜか「東京でテロは起きない」と無邪気にも信じ込んでいる風潮があり、私にとってはそれがとても不思議で仕方がなかった。日本もアメリカ支持を堂々と表明し、当然、日本もその標的となる。私にはそれがとても現実味を帯びたものとして思え、本作を執筆しようと筆を執りました。あれから数年を経て、「多様化」や「ダイバーシティ」などと言われていますが、いまだに「自分と違う立場」を理解しようとせず、排他的になる。その風潮、危うさは今も変わっていないように感じます。
世界を踏み留まらせる力
本書のサブタイトル「AndsothisisXmas」は、ジョン・レノンの「HappyX-mas(WarisOver)」の歌詞の一節だ。
ジョンのこの曲は、本作の構想にすごくマッチしたんです。誰もが知っている昔の曲ですが、いまだに戦争のない世界は実現していないし、平和とは言い難い。その人間の愚かしさや浅ましさを感じていて。それでもやはり彼がこの曲を残してくれたからこそ、少しはマシな世界になっているとも言えます。
もしかしたらエンターテインメントの力で、この世界は何とか踏み留まっているのかもしれない。私自身、その端くれとして、「エンターテインメントの力」を信じたい。そういう意味でこの曲は、本作の創作過程において、とても大きな力と様々なイメージを与えてくれました。
秦さんが言う「エンターテインメントの力」とは何なのか。
私は、嘘くさいハッピーエンドは大嫌いですが(笑)、一方で「現実が苦いから、現実の苦さを描く」というのも違うと思っていて。悲惨で悲しい話もたくさん出てくるけれど、最後には明日への希望も少しある。そのバランスをうまくとりながら、地に足の着いた、リアリティのあるエンターテインメントを描きたい。人は面白いものに触れるとポジティブなエネルギーを発します。多くの人やこの世界がそのエネルギーで満ちていてほしいと願っているし、それをかなえるのが「エンターテインメントの力」だと思います。
だから自分の主義主張が前面に出ることで、エンターテインメント性が損なわれるのであれば、私はそういうものを、お金を払ってくれる読者に届けたくはない。まず「読んで楽しい」が大前提にあり、そのうえで少しだけ自分の思いを語らせてもらう、それくらいが丁度いいのではないかと思います。

▲映画キャストを配した店頭用A4パネル
命を落とした人たちの「日常」
本作ではアパレルショップで勤務する女性、上司に仕事を依頼された独身のサラリーマンなど、爆破テロで命を落とす、本筋とは関係のない些細な人物の「普通の生活」、「日常」も描いている。
テロで命を落とす人たちは、決して匿名の人ではなく、彼ら彼女らにも日常があり、生活があることを描かないといけないと思いました。なぜなら爆破テロで「知らない人が亡くなりました」では、読者の心は揺さぶられないし、彼ら彼女らに寄り添うこともできない。
そういった些細な人物を多く登場させることで、もし現実にテロが起きた場合、読者に「自分もテロで命を落とすかもしれない」、「これは自分の話なのかもしれない」と思ってもらいたくて、あえて描いています。
主要な登場人物ごとの視点で章立てされており、まるでリアルタイムで事件が進行しているような錯覚を起こす構成だ。
私自身、映画やドラマの脚本なども手掛けていますが、やはり小説ならではの、読書ならではの体験をしてほしい。またお読みになっていただければわかりますが、墨ベタ白抜きのページを数ページ挿入しています。これは視覚的にも「ドキッ」とさせますし、サスペンスフルな本作では効果的です。これも小説でしかできない演出です。ドラマの脚本で「次週に続く」とか、CMまたぎの引っ張りなどが体に染みついているので、それを小説にも取り入れようと思って、この手法をとらせてもらいました。これもまずは「読んで楽しい」と思ってもらうための工夫のひとつです。

▲秦さんが演出の上で、こだわったという墨ベタページ
ドラマの脚本、映画監督などいろいろな顔を持つ秦さん。小説執筆とその他のクリエイティブな行為との違いは。
小説は基本、一人で創りあげるものなので、その反響や責任は100%自分自身が受ける。でもチームで作るものは、化学反応が起きる。それこそ映画監督やキャスト、美術担当だって一人違えば、作品は大きく変わってくる。そのチームでしかできない作品になる。そういう面白さ、ドキドキはあります。
今回、映画化しましたが、実は台本チェックもしていないし、撮影現場にも行っていません。映画が出来上がってからしか見ていないんです。これは今回に限らず、私の作品を映画化していただく際はすべて同様です。原作者が口出しするといいものはできない。
やはり映画チームには映画チームで、創りたいもの、伝えたいことというのがあって、それは尊重しなければならない。それが許せないのであれば、映画化を断ればいいだけの話です。
だから原作と映画作品はまったく別モノで、どちらも連続爆破テロを軸としてストーリーは進みますが、小説が描いたものと映画チームが描いたもので、また違うと思うんです。それぞれが違う広がり方をして、この「サイレント・トーキョー」という一つのコンテンツが、より立体的になってくれればいいと思います。
大切な「当たり前」を失うことへの切実さ
映画撮影が新型コロナウイルスの影響を受ける前だったことから、延べ1万人のエキストラを配して、舞台となる渋谷を再現したという。
渋谷でのシーンは、今のコロナ禍では考えらないほど、多くの人を入れて、撮影しています。これもほんの少し前なのにもかかわらず、遠い過去のようにも見える。こういう方法で映像が撮れる日がまた来るのだろうかと思うと、それもある種「当たり前だった現実が、ある日突然失われる」ということのいい例だと思います。
それは「渋谷のスクランブル交差点が今は平和だ、でも明日はわからない」、「大切なものが突然なくなる可能性がある」、そういったことを象徴するような群衆シーンです。ですから、小説でも映画でもどちらからでもいい。「もしかしたら東京でテロが起きて、自分の命や大切なものが失われるかもしれない」ということを切実に感じ取ってくれたら、それは著者としてとてもうれしいことだし、できればその両方に触れてもらうことで、そのことをより多面的にとらえてほしいと思っています。

文庫判/320㌻/本体680円
秦 建日子(はた たけひこ)

小説家・脚本家・演出家・映画監督。04年『推理小説』で小説家デビュー。同作は「アンフェア」としてドラマ&映画化され、続刊と共に《刑事雪平夏見》シリーズはベストセラーに。他に『KUHANA!』等著書多数。
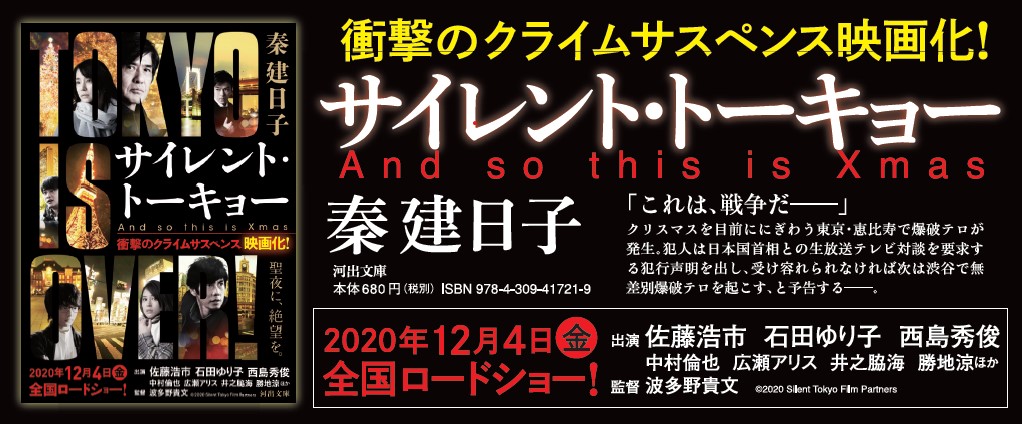


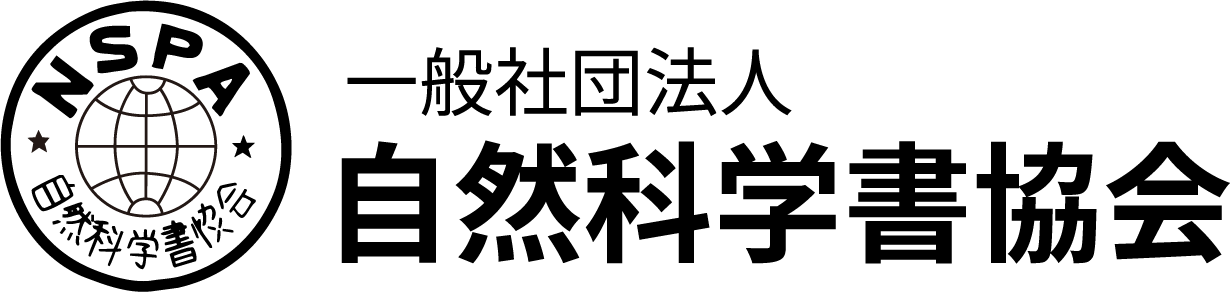


コメント