
本屋大賞で2度に渡り、2位となった青山美智子さんの最新刊『月の立つ林で』(ポプラ社)が11月上旬に刊行される。月を題材とした本作は、姿の見えない誰かに私たちの日常が支えられていることを教えてくれる。コロナ禍で見えない誰かとのつながりを強く感じたことが執筆したきっかけだと語る青山さんに、本作への想いについて聞いた。
(聞き手:山口高範)

見えないが確かにそこにあるもの
月、特に新月を中心に各章の物語は進む。なぜ新月を題材にした作品を書いたのか。
コロナの影響が想像していた以上に続く中で、「見えない人とのつながり」を強く感じたんです。例えばスイッチひとつで電気がつき、蛇口をひねれば水が出てくる。それは当たり前のことですが、家にいなくてはいけない状況で、姿も見えない誰かが、私たちの生活を確かに支えてくれていることを以前より強く実感するようになりました。
私にとってはSNSもそうで、人と会えない状況で、どんなに離れていても、同じ時間に誰とでもつながることができる、安心できる命綱のように感じたんです。
コロナのことを直接書く勇気は私にはなかったけれど、その「見えないつながり」というテーマであれば書けるかもしれない。そこで「見えないけど確かにそこにあるもの」って何だろうと編集の方と話していたら、「それって真昼の星みたいなことですかね」と何気なく言われたんです。「そっか、真昼の星か」と一人で考えていたら、「ああ、新月もそうだな」と思って。新月ってそこにありはするけど見えない、それってすごいことだなと。もともと月が好きということもあって、私が抱えているものと月とを連動させることで、お話を創ることができるかもしれない、と思ったのがきっかけです。
本作では「ツキない話」というポッドキャスト、また全章に登場する、主人公らとは真逆の存在である朔ヶ崎佑樹が重要な役割を果たす。
「ツキない話」のタケトリ・オキナはただ月の話を配信しているだけで、それを聴く各章の主人公たちの顔も知らなければ、互いにどこの誰かもわからない。そこには物理的な距離があるんですが、でもその距離が今の世の中には必要だと思うんです。
これだけSNSやYouTube、アプリなどが発展して、誰でも発信できるし、誰とでもつながることができる。そういう距離があるからこそ成立している世界というものが、私たちの目の前にはあって、その中で自分たちが何を取捨選択していくのか、それが実は人生を変えることになるかもしれないと思います。
一方で距離が近すぎるがゆえに見えないということもあって、常に一緒にいる家族とか、目の前にいるからこそ、見えないことってあると思う。そういったことも描きたかったですね。
各章の主人公たちは、例えるなら月です。でも佑樹はまるで太陽のような存在です。それを象徴するように、彼が所属する劇団名の「ホルス」はエジプトの太陽神で、アルバイトをしているバイクショップの名前は「サニー・オート」。それは私の遊びみたいなもので、読者がそれに気づいてくれたらうれしいです。
四章はイタリア製のバイク「ベスパ」を愛する女子高生が主人公だ。
最初に人ではなく、機械しか信じない女の子を描こうと思って、何か無機質だけれども相棒になりそうなものはと考えたときに、おしゃれで、かわいらしい「ベスパ」がいいなと。
でも私はバイクも乗らないし、全然知らない。だから自宅近くにあるバイクショップにお客のふりして行ったんです。取材しますって言うと、お互い嘘が出ちゃうかなと思ったので。
そこのオーナーさんにいろいろとお話を聞かせてもらいました。実は三章の主人公の整備士は、そのオーナーさんがモデルなんです。作中に「ぐったりしていたバイクが俺の手で息を吹き返し、エンジンがかかった瞬間は得も言われぬ多幸感に見舞われる」という一文があるんですが、それはそのオーナーさんの言葉を使わせていただきました。
原稿を読んでいただいたときに「整備士を代弁してくれる言葉です」みたいなうれしいことも仰ってくれましたし、小説を書いていることで新たな出会いがあるということが、何よりもうれしかった。
誰かに向けて書く
作中に「月はエンタメ」という台詞があるが、青山さんは小説という表現をどう考えているのか。
エンターテインメント小説というのが正直わからなくて。私の作品がエンタメなのかどうなのかもわからないですし、難しいですよね。
ただそれはエンタメとは違うかもしれないけれど、小説の素晴らしさは「こうしなさい」、「こうしなくてはいけない」と押しつけないところだと思っていて、それをどう読むか、どう思うかは、それぞれの読者の方次第だと思っています。ですから何か作品に込めたメッセージとか、作品で伝えたかったことは何ですか、と聞かれると困ってしまう。
もちろんエンタメって思っていただいてもうれしいし、学校や塾の教材によく使っていただくこともあって光栄ですし、暇つぶしとして役立てたらそれもいい。でも作品として「面白くなくてはいけない」とは思います。それをエンタメということであれば、そうかもしれません。
小説を書くにあたっては、「誰かのために書く」というよりも、「誰かに向けて書く」という気持ちはあります。本はこの世の中にたくさんあって、その中から私の作品を手にとって読んでくれている。それってすごい縁で、巡り会えたその人に向けて書いていると言っていいかもしれない。その人が私の作品から何かを受け取ってくれたら、それはとてもうれしいことです。

脇役にスポットを当てる
青山さんの他の作品同様、本作もまた一人称のオムニバス形式で物語は進む。
デビュー作の『木曜日にはココアを』(宝島社)から、ずっとこのスタイルで書いています。バトンを渡していくようなこの書き方が、私には合っているし、書きたいことを書ける一番の手法なんです。
映画やドラマを見ていても、主人公ってすごくしゃべりますよね。当たり前の話なんですが。でも私はあまり台詞のない脇役とか、レストランなどのシーンで隅のほうで話しているエキストラの人とか、「一体、何を話しているんだろう」って気になってしまうんです。だから本編に全然集中できない(笑)
私の作品の中でも、そういう人たちにスポットを当てたいという思いもあって、こういうスタイルで書いています。本作の主人公たちは、口下手の人たちばかり。だからここぞというときの台詞は、短いけれど、そこに感情や本心みたいなものがすごく表れているように思います。
私の作品は出版社をまたいで、いろんな登場人物が他の作品にも必ず登場するんです。よく出版社の方から長編執筆の依頼なども受けるんですが、私にとってはすでにものすごく長い長編小説を書いているつもりなんです。しばらくはこのスタイルで書き続けようと思っています。
これまで本屋大賞を2度にわたり2位に選ばれるなど、書店員からの支持も厚い青山さん。最後に書店員に向けたメッセージを聞いた。
今作のテーマとも重なる部分もあるんですが、姿が見えないけれど、支えてくれる人というのは確かにいて、私にとって書店員さんがまさにそういう存在なんです。
こういう状況下でなかなか訪問もかなわないなか、今でも応援してくださっている。最初のデビュー作『木曜日にはココアを』も書店員さんが面陳してくださったことで、読者の方が気づいてくれた。
本屋大賞で2位になれたのも書店員さんのおかげですし、そういう応援があって、私は初めて作家としての命を続けさせていただいているということを強く感じていますし、書店員さんからの気持ちも、決して見えるものではないけれども、届いています。感じています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
青山 美智子(あおやまみちこ)
1970年生まれ、愛知県出身。大学卒業後、シドニーの日系新聞社で記者として勤務。2年間のオーストラリア生活ののち帰国、上京。出版社で雑誌編集者を経て執筆活動に入る。デビュー作『木曜日にはココアを』が第1回宮崎本大賞を受賞。『お探し物は図書室まで』、『赤と青とエスキース』で本屋大賞2位に選ばれる。その他『鎌倉うずまき案内所』、『ただいま神様当番』など著書多数。


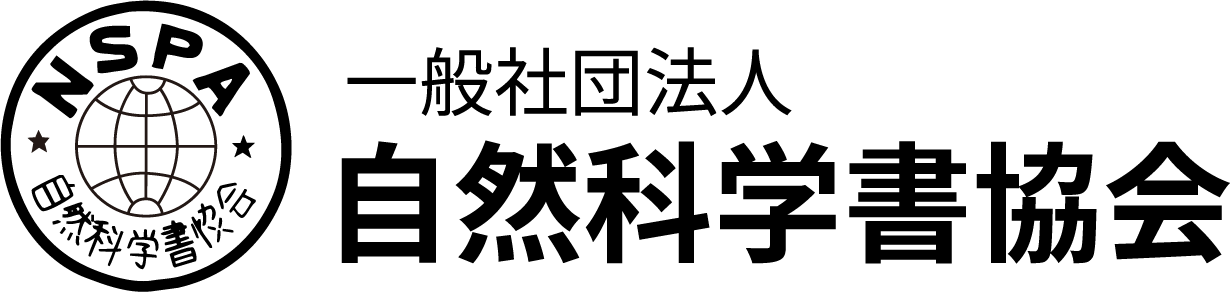


コメント